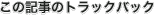日記兼二次小説スペースです。
あと、時々読んだ本や歌の感想などなど。
初めての方は、カテゴリーの”初めての人へ”をお読みください。
カレンダー
カウンター
フリーエリア
カテゴリー
プロフィール
HN:
yui
性別:
非公開
自己紹介:
典型的なB型人間。
会社では何故かA型と言われますが、私生活では完全なB型と言われます。
熱中すると語りたくなってしょうがない。
関西在住、性格も大阪人より。
TVに突っ込みを入れるのは止めたい今日この頃。
趣味は邦楽を愛する。お気に入り喫茶店開拓
一人が好きな割りに、時折凄く寂しがりやです。
字書き歴7年近く。
インテリ好きですが、私は馬鹿です。
コメント、トラバはご自由にどうぞ。
メールアドレス
yui_control☆yahoo.co.jp
☆→@
会社では何故かA型と言われますが、私生活では完全なB型と言われます。
熱中すると語りたくなってしょうがない。
関西在住、性格も大阪人より。
TVに突っ込みを入れるのは止めたい今日この頃。
趣味は邦楽を愛する。お気に入り喫茶店開拓
一人が好きな割りに、時折凄く寂しがりやです。
字書き歴7年近く。
インテリ好きですが、私は馬鹿です。
コメント、トラバはご自由にどうぞ。
メールアドレス
yui_control☆yahoo.co.jp
☆→@
最新記事
最新TB
ブログ内検索
最古記事
アクセス解析
かなりお久しぶりなメンバーで食事に行ってきました。
中学校の頃に仲の良かった5人組です。
中学校の頃に仲の良かった5人組です。
通称5バカ。
良くも悪くも根に持つこともなく、気を使うこともない5人組で中学校の頃は、それはもう揃ってしゃべり倒しておりました。
それぞれまったく違う高校に進むと、それぞれで連絡を取ることはあっても、全員が揃うというのが、難しい面々で。
うち一人は、3年ほど一緒に同人やってた相方でもあるんですけど。
なので、全員揃うのは、成人式以来ではないかと思います。
それが今日はタイミングが合ったのか。
地元で夜なら全員集合が可能だというこで、地元の焼肉屋で
おおはしゃぎ★
はい、もう20代半ばを過ぎた娘が5人。
揃ってお酒が入れば、肉を取り合うただのおっさんです。
ははは・・・私この年になって、店員に
「他のお客さんがおられますので、もう少し静かにお願いできますか?」といわれるとは思わなかった。
っていうか、今までも無かったのに。
なんだこのメンバーのテンションの高さは。
はしゃぐはしゃぐ。
肉取り合いだし、半生で食べそうになるし、いつの間にかなくなってるし。
このメンバーはやっぱり楽しいです。
みんなそれぞれに仕事をしていて、全然違う職種で。
職種が違えば仕事に対する悩みも違うはずなんだけどなぁ。
何故か被る。
久方ぶりに会ったTちゃんは、保母さん。
どうもバイト契約らしくって、仕事の区分けがしにくいとか。
まぁそれは私も悩むところで、向こうも向こうでどこまで知っていいのかが解らないけど、保母さんは保母さん。
お母さんから見たらバイトだろうと正社でも同じというジレンマ。
それは販売員のHちゃんも同じだったり。
プログラマーのRちゃんは、下が妙に頑固で指導が大変だとか。
そういう話を聞きながら、うわぁ~とか思ったり。
特に販売員のHちゃんの話は、かなりどギツイというか。
大きな会社は大変だなぁというのが・・・。
このメンバーは仕事に対して、ある意味とても厳しい部分があって。
仕事に対してというか・・・・ぶっちゃけお金を稼ぐということに関しては貪欲というか。
でもその分仕事に対するプロ意識はとてもある。
その仕事をしている者としてのプロ意識と言うようなものだと思う。
だから仕事に対しての姿勢は同じなので、技術的なこと以外であれば、共感できる。
私自身も電話先の困ったお客さんなんて・・・私も有りましたよ。
解らなかったら直ぐに人に教えてもらおうとする人。
コラコラって・・・・。
人に聞くなとは言わない。
人に聞いてもいい。
でもそれは、最終手段であることを忘れるなと言いたい。
調べろ。
辞書でもネットでもとりあえずやってみるでもいい。
でないと教えようにも教えられないでしょって思う。
出来ないところって、ぶつからないと見つけられないんですよ。
で、間違えたところを修正して、初めてやり方ってわかるものなんですよ。
そういうことを繰り返していくことで、応用が出来るようになるんです。
それが当たり前だという認識のHちゃんは、それをしない人が理解できないらしい。
まぁ無理ないよな。
でも彼女いわく、私はそういうのが出来ているとのこと。
よかったぁ・・・・。
でも私のこういう姿勢は、塾で培ったものなんですけどね。
人に聞くって、教えてくれる人の時間を割くってことなんですよね。
その教えてくれる人が、他のことに使うはずだった時間を、私の勝手で使うですよね。
それって凄く申し訳ないこと。
でも、向こうは好意で教えてくれるんだから、こちらも最低限の礼儀を通さなきゃいけない。
それが、調べるって行為なんだと思う。
初めて教えてもらうのならば、メモを取るってことなんだと思う。
調べて”私はここまでやったけど、コレ以降のやり方がわからないです”とか”ココまでやったけど、ココがどうしても理解できない”とか。
貴方は今どこにいるのかを教えてほしい・・・って。
ただ”教えて”では教えようがないんです。
本質は理解もできません。
こっちも間違えたところを見ないと、貴方が何がわからないかわかりませんって。
貴方の現在地を教えておくださいって。
あと、メモもね。
最初って、どうやってメモを取っていいかもわからないですよね。
それでいいと思います。
だって、全部一言一句メモを取れるわけ無いもん。
メモを書いたものが意味不明でもいいんです。
だって、解る人から見れば、それが意味が通ることもあるから。
後で聞いてもらったら、そのメモを完成させてあげることもあるから。
書類とかだったら、許可を取って可能であれば、コピーをとってもいい。
書類に注意を書いたりとか、メモを後で清書すればいい。
体を使う仕事でなければ、こういう風に勉強のやり方ってあると思う。
人にものを教えてもらう姿勢ができて居ない人が余りに多い。
話を聞けない人が多い。
コレは全員共通していました。
解らないことは、まず調べる。
教えてもらうのは、その後です。
そして、考えるのツールを学ぶのが義務教育なんですよね。
それが勉強の仕方を学ぶということなんですよね。
コレが駄目なら、この方法って・・・・その感覚を養う場所なんです。
1+1=2だったのが掛け算になって、分数になって、少数になって、乗数になって、微分だとか方程式とか。
記号が出てきたりとか。
単純に1という数字がそれを倍にしたりとか、1より小さくなったりとか。
そういう考え方のツールを養うのが数学。
音を使って、感情や声を学ぶ音楽。
薬品を使ったり、道具を使って何かの反応を見たり、まったく違う物質を作るのが、化学や科学。
説明書を読んでそれを理解して、物を作る技術。
食品を使って、味を使う家庭科。
体を使えば体育だし、歴史や現在の世界から読み解くのが社会。
みんな言います。
義務教育のやっていることは、将来使わない。
確かに、勉強したことそのものは使わないかもしれません。
でも、勉強の仕方、それを理解するのにやった方法は、将来絶対必要になってきます。
それは断言できます。
そういう中で人に話を聞く方法が出来るようになるんです。
でもコレって出来るできないって年齢に関わらずだから、結構やっかいなんですよね。
一人は本当に悩んでいて、かわいそうでした。
私?私はそういう客は客じゃないと思ってましたから。(笑)
PR